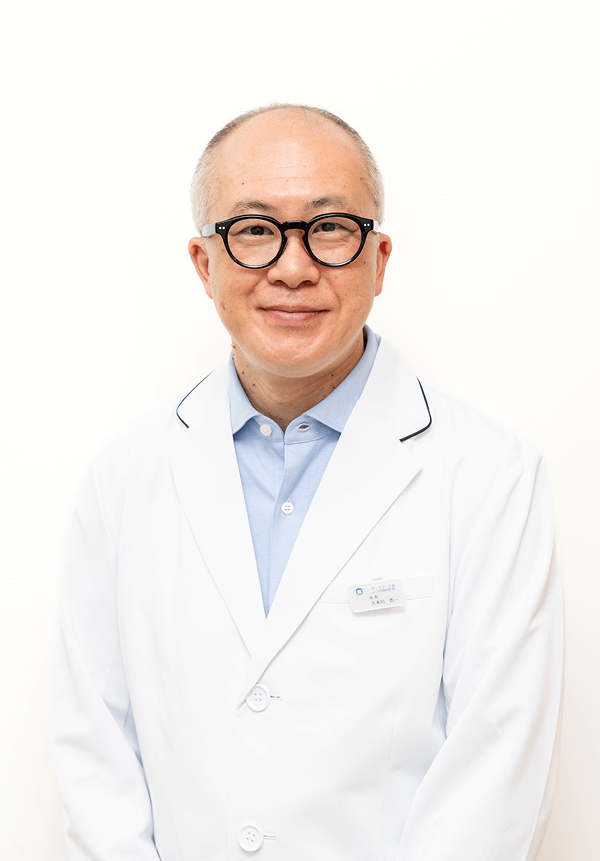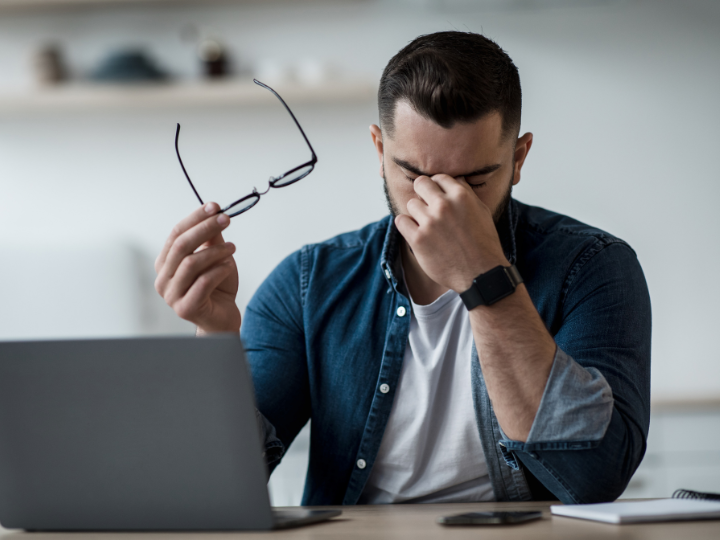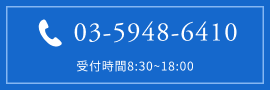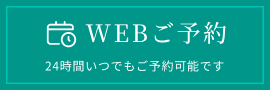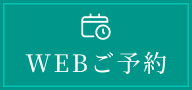01
レーザー光凝固術
レーザー光凝固術は、
糖尿病網膜症の進行を抑えるために行われる代表的な治療法
です。
網膜の虚血部分にレーザーを照射して、新生血管の発生や網膜出血を予防することを目的
としています。
レーザーによって網膜の酸素需要を減らし、網膜全体の循環状態を改善させる効果があります。
治療は外来で行うことが多く、点眼麻酔を用いて短時間で実施できます。
治療後は視界に一時的なかすみや暗点を感じることがありますが、日常生活に大きな支障をきたすことは少ないとされています。
ただし、視力を回復させる治療ではなく、あくまで「これ以上進行させないこと」を目的としている点に注意が必要です。
[イエロースキャンレーザ光凝固装置 YLC-500Vixi™]
当院で使用しているイエロースキャンレーザ光凝固装置 YLC-500Vixi™は、眼科領域で広く用いられている最新のレーザー治療機器のひとつです。
波長577nmの黄色レーザーを採用しており、網膜の血管や黄斑部に対して選択的に作用しやすく、周囲の組織へのダメージを最小限に抑えられるのが特徴
です。
従来のレーザー装置に比べ、
痛みや術後の炎症が少なく、視力に直結する黄斑部付近の治療にも適しています
。
また、マルチスポット照射やスキャンパターン機能により、短時間で効率的に治療を行うことができ、患者様の負担軽減にもつながります。